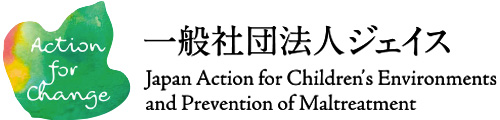代表理事 ごあいさつ
日本にいるすべての子どもたちが、
心から自然な笑顔があふれ出る時間をたくさん持てる社会
身体的・精神的・社会的にウェルビーイング[i]な状態で暮らせる社会
を目指して、2021年5月17日、これまでさまざまな形で共に活動してきた仲間と、一般社団法人ジェイスを立ち上げました。
ジェイスは、子どもたちの育つ環境の課題に気づき、改善に取り組む団体です。
たとえば、
- 子どもたちの育ちに関わる大人が、子どもと子どもの育つ環境について学ぶ機会を提供します。
- 子どもたちのウェルビーイングを実現するための研究を行います。
- 子どもたちの育ちに関わる大人をサポートします。
- 子どもへのマルトリートメント[ii]を予防するための広報や啓発に取り組みます。
大人はかつて子どもだったのですが、だからといって、子どもの扱いがわかっているわけではありません。
気づかないうちに、子どもたちに対して不適切な関わりをしてしまうことがあります。
私もそうです。
だから、
- いろいろな大人たちが協働してさまざまな子どもたちにいろいろな角度から関わること
- 関わり過ぎないで見守ること
- 間接的に子どもの育つ環境づくりをすること
を通して、子どもたちのウェルビーイングを保障することが必要になります。
ジェイスの中心的活動は、予防的な活動です。子どもが大変な思いをしながら生きなければならないような状況の予防を目的として、ジェイスは具体的な活動をしていきます。
発達を阻害されている子どもたちに対してよりよい養育環境を作ろうと試みます。
予防の成果は可視化することが難しいのですが、何もしなければ、子どもたちの発達は、阻害していると気づかない、ときに善意の人たちによって、ますます阻害されてしまうからです。今の日本は、子どもたちの生活や遊びを通した体験が限定的なものになっています。経済的な貧困状態にある子どもは7人に一人と言われますが、体験の貧困状態にある子どもたちはもっと多いと言えるでしょう。
体験が限られる環境は、発達を阻害する可能性があります。
そのような状況を放置しておいたり、助長したりすることを、私たちは社会的マルトリートメントと呼んでいます。
社会は常に発展し、子どもたちの生育環境はよくなっています。その一方で、社会が便利になればなるほど、自然に発達できない環境が拡がっています。今、大丈夫な環境も、あっという間に子どもたちの発達を阻害する環境になり得ます。
大人が良かれと思ってすることが、子どものウェルビーイングを阻害してしまうこともあります。
みんながそうしているからと同じようにしていると、子どもたちをその環境においておくことがマルトリートメントになる場合があります。子どもの発達を阻害する養育環境に気がついたら、私たちは情報と技術を提供して、その環境を変えていく努力をしたいと思います。
「知る。つながる。動く」
つまり、子どもの養育環境に関する知識やそれを改善する技術を得て、さまざまな人とつながって、 自分の強みを活かして具体的な活動を行う。
ここまでの一連の動きができる人を、ジェイスは増やしていきたいと思います。
私たちの団体を知った皆さま。
どうぞ私たちとつながり、私たちと一緒に動いてください。
ふんわりとひろがるコミュニティを作っていきましょう。
よろしくお願いいたします。
2025年4月1日 一般社団法人ジェイス 代表理事 武田 信子
団体概要
| 団体名 | 一般社団法人 ジェイス Japan Action for Children’s Environments and Prevention of Maltreatment |
| 設立年月 | 2021年 5月 |
| 代表理事 | 武田 信子 |
| 理事 | 神林俊一、築地律、西川正、古野陽一、松田妙子、横須賀聡子 |
| 監事 | 森田圭子 |
| 主要事業 | 研修、調査研究、出版 、普及啓発 、相談・コンサルテーション、社会環境の改善、等 |
| 定款 | 一般社団法人ジェイス 定款 |